3億円のIT投資×30年以上の漫画文化で目指す"創造的復興"とは?湯前町がCGプロダクションを誘致する理由

熊本県の南部、宮崎県との県境に位置する人口約3,400人の町、湯前町。豊かな自然と、700年以上の歴史を持つこの小さな町が今、デジタルコンテンツをはじめとするIT企業の誘致に力を入れている。その背景には、全国の地方自治体が直面する人口減少という課題、そして令和2年7月豪雨災害からの「創造的復興」への強い意志があった。
この先進的な取り組みを牽引する湯前町の長谷和人町長と、町職員の坂本好氏にインタビューを実施。「漫画の町」として四半世紀以上の歴史を積み重ねてきた文化的な土壌と、新たに整備される高速インターネット網やサテライトオフィス。これらを融合させ、クリエイターにとっての理想的な環境をいかにして築こうとしているのか。町の未来をかけた挑戦の全貌に迫る。

長谷和人 町長
「漫画の町」の歩みと人口減少への危機感
CGWORLD編集部(以下、CGW):本日はよろしくお願いします。まず、湯前町がデジタルコンテンツ企業の誘致を始めた背景から伺えますか。
長谷和人町長(以下、長谷):湯前町には昭和35年時点で約9,000人の人口がいましたが、今では3,400人を切ってしまいました。生産年齢人口もいわゆる逆三角形の構造になり、このままでは町が立ち行かなくなるという強い危機感がありました。そこで、何か新しいコンテンツで町を活性化させなければならないと考えたのが始まりです。デジタル分野の企業誘致を行うことで、新しい人のながれ、いわゆる「関係人口」を生み出せるのではないかと。
CGW:その中で、なぜ「漫画」が重要なキーワードに?
長谷:実は湯前町は平成4年から「漫画の町」を宣言しているんです。これは、『アンパンマン』のやなせたかし先生の盟友で湯前町出身の風刺漫画家・那須良輔先生がご縁です。那須先生が亡くなられた後、その功績を称えて熊本県のアートポリス事業で「湯前まんが美術館」を建設しました。以来、四半世紀以上にわたり、毎年11月には「ゆのまえ漫画フェスタ」を開催し、「那須良輔風刺漫画大賞」も継続するなど、漫画文化を町の核として育んできました。
CGW:長い歴史があるのですね。
長谷:そうです。「マンガ県くまもと」の中でも、真の漫画の町づくりは湯前から始まったと自負しています。この文化資本を未来に繋げるため、3年前からは文化庁の補助事業を活用し、傷み始めていた那須先生の原画約7,500点のうち6割ほどをデジタルアーカイブ化しました。これは文化財の保存だけでなく、将来的にはデジタルコンテンツとして販売するなど、「見る漫画」から「稼げる漫画」への展開も視野に入れています。
CGW:「漫画の町」としての歴史の深さに驚きました。
長谷:那須先生だけでなく、『仮面ライダーSPIRITS』の村枝賢一先生や、『うしおととら』で有名な藤田和日郎先生など、第一線で活躍されるコミック系の先生方にも毎年イベントで来ていただいています。ただ、本町の漫画の町としての原点は那須先生が描かれていたひとコマ風刺漫画の文化です。手塚治虫先生も所属された「漫画集団」のながれを汲む、種村国夫先生のような風刺漫画家の先生方との繋がりも、町の根幹として大切にしています。コミックと風刺、両方の文化があってこその湯前町なんです。
CGW:アニメとの連携もされていますよね。『夏目友人帳』のイベントは反響が大きかったとか。
長谷:すごい反響でしたよ。『夏目友人帳』は作品の舞台が熊本県の人吉・球磨地方がモデル地ということもあり、湯前町も舞台のひとつなんです。
全国からはもちろんですが、昨年は台湾からも熱心なファンの方がこのイベントのために駆けつけてくれました。作品の持つ力が、国境を越えて人をこの小さな町に呼んでくれる。その熱量を目の当たりにして、我々の取り組みの可能性を改めて感じました。
災害復興から生まれた最先端の創作環境
CGW:企業誘致のための環境整備はどのように進んでいますか?
長谷:我々は、令和2年7月豪雨災害からの復興を「創造的復興」と位置付けています。この災害で、町の終着駅であるくま川鉄道の橋梁が流失し、大きな被害を受けました。
CGW:甚大な被害だったと記憶しています。
長谷:特に日本三大急流のひとつである球磨川にかかる「第四橋梁」が完全に流されてしまったのが決定的でした。あれで鉄道網が寸断され、まさに陸の孤島のような状態になったのです。ですから、復興は単に線路を繋ぎ直すだけでなく、この鉄道の全線開通を町の「第2の創業」と位置付け、未来に向けた投資を集中させる好機だと捉えました。リニューアルする各施設は、全て鉄道の駅から歩いてすぐの場所に集約させています。来年上半期に予定されている全線開通に合わせ、駅前周辺の再開発を急ピッチで進めているところです。
CGW:再開発とは、具体的にはどのような施設でしょうか。
長谷:まず、駅前の交流施設「レールウィング」や「湯前まんが美術館」の大規模リニューアルです。そして、美術館内にあった図書館を独立させ、新築しました。その一環として、クリエイターの方々がすぐに使える「サテライトオフィス」も駅のすぐそばに建設中です。若者向けの住宅整備や宅地分譲も並行して行い、職と住の両面からサポートできる体制を整えています。
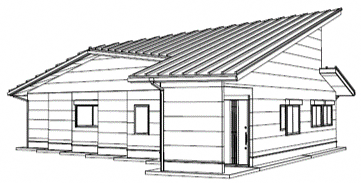
CGW:デジタルコンテンツ制作で重要なインフラについては?
長谷:まさに、それがわれわれの最大の強みのひとつです。実は、一度町内に光ファイバー網を整備したのですが、速度が十分ではありませんでした。そこで、3年ほど前に再度大きな投資を行い、回線を全面的に入れ直したのです。
CGW:2度も投資を。
長谷:はい。町独自の予算で総事業費として約3億円をかけました。これは光ファイバー網の全面更新、高速通信機器の導入、そして町内全域への安定した高速インターネット環境の構築に充てられています。 デジタル社会において通信環境は水道や電気と同じインフラの基礎です。
これがないと何も始まらないと判断しました。おかげで今は、都市部と遜色ない高速通信が可能です。大容量のデータを取り扱うCG・映像クリエイターの方々にも、ストレスなく作業していただける環境が整ったと自負しています。このインフラがあるからと、東京の会社を畳んで湯前町に移住し、デジタル設計の事務所を起業された方もいらっしゃいます。
「小さな町」だからできる手厚い支援と地域との繋がり
CGW:湯前町に進出した企業はどのような支援制度を利用できますか?
坂本 好氏(以下、坂本):実務を担当している湯前町企画観光課の坂本です。支援制度については町の単独事業として、サテライトオフィスの家賃補助制度を設けています。月額5万円を上限に、1年目は全額、2年目と3年目は半額を補助するもので、県の制度とも併用可能です。
また、移住支援金として一世帯につき100万円、単身の場合60万円、18歳未満のお子さんがいる場合は1人につき100万円が加算されます。
CGW:手厚いですね。暮らしの面でのサポートも?

坂本:お子さんがいるご家庭のために、高校3年生までの医療費無料化、保育料の無償化、小中学校の給食費補助などを実施しています。また、空き家をリフォームして住む方への補助金制度や空き家バンクなどもあり、住居探しのサポートも行っています。ご家庭の経済的負担をできるだけ軽減し、安心して創作活動に打ち込めるような取り組みに力を入れています。
CGW:小規模な自治体だからこそのメリットはありますか?
長谷:意思決定の速さですね。ワーケーションで町を訪れた企業さんから「町のイベントのLP(ランディングページ)をつくりたい」というご提案をいただいた際も、「やろう」と決めれば、数ヶ月後にはもう着手している。このスピード感は、大きな組織にはない強みだと思います。何かやりたいことがあれば、すぐに相談して、一緒にかたちにしていくことができます。
CGW:創作活動の拠点としてだけでなく、地域との関わりも魅力になりそうですね。
長谷:はい。私たちはただ場所を提供するだけでなく、地域との繋がりも大切にしています。希望があれば、500年以上の歴史を持つ球磨焼酎の蔵元や、手仕事で狩猟道具やキャンプ用品をつくるユニークな鍛冶屋さんなど、地元の事業者さんを紹介できます。
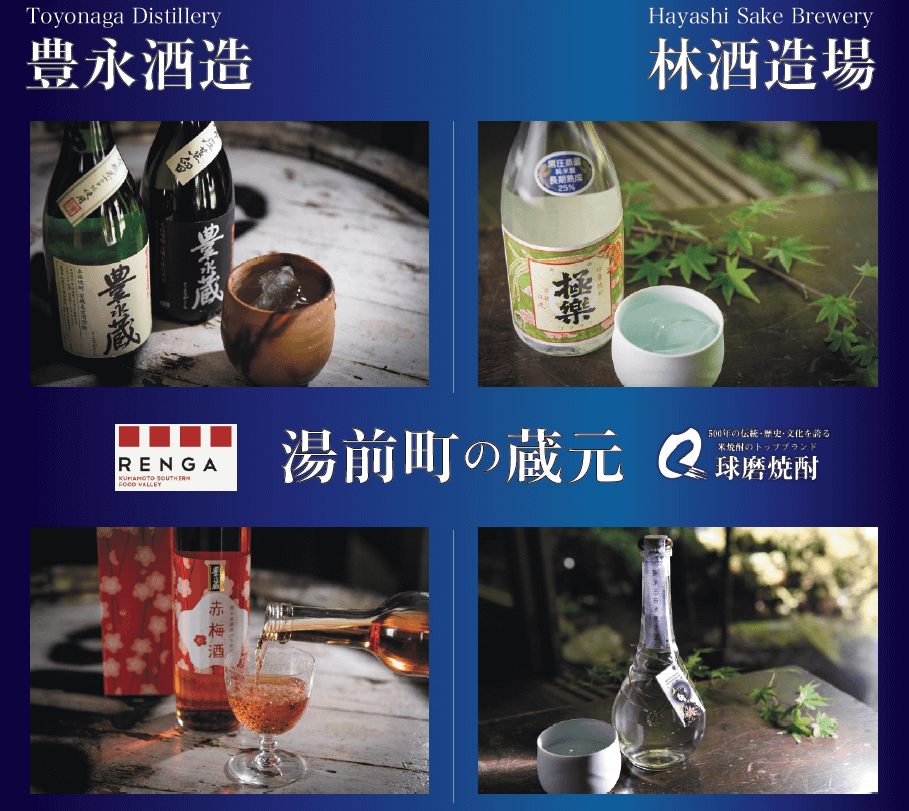
長谷:また、町内には鎌倉時代創建の城泉寺といった歴史遺産や、有馬温泉と同じ泉質の「ゆのまえ温泉ゆらり」もあります。こうした地域の資源に触れることが、新たなクリエイティブの源泉になるかもしれません。
CGW:実際に移住された方々は、どのような経緯で湯前町を選んだのでしょう。

長谷:ひとつ面白いご縁をご紹介します。もともと町内にあった携帯電話関連の工場が移転して、建物が空いていたんです。そこへ、奥様が球磨郡出身だという方がいると聞きつけて。ご主人は広島の方でしたが、我々も東京の板橋区にあった会社までお伺いして、「ぜひ湯前で」と口説き落としました(笑)。やはり決め手は、すぐに事業を始められる「ハコ(工場跡)」があったことと、奥様の故郷への想い。そして我々の熱意だったのかもしれません。
CGW:ワーケーションで来られた30社の方々の反応はいかがでしたか?

坂本:皆さん、本当に様々な目的で来られていました。企業の福利厚生や合宿、経営者仲間での視察旅行など。業種もIT系が中心ではありましたが、中には都内で飲食店を経営されている方もいらっしゃいました。最初は我々も手探り状態でしたが、3年間で多様な方々の声を聞く中で、「湯前町に合うのは、やはり場所に縛られずに創造的な仕事をするデジタル系の企業ではないか」という現在の方向性が見えてきました。
テクノロジーと教育で描く、持続可能なクリエイティブタウン
CGW:デジタル技術の活用について、他に特徴的な取り組みは?
長谷:商工会の青年部が主体となって、町の各所にARコンテンツを設置しています。スマホをかざすと那須先生の作品が現れたり、人気アニメ『レヱル・ロマネスク』のキャラクターが駅前に出現したりと、町歩きが楽しくなるしかけです。

長谷:また、豪雨災害の経験からドローンを導入し、防災に活用するだけでなく、町長室からリアルタイムで空撮映像を確認できるシステムも構築しました。ドローンに荷物を載せて自動航行させる実証実験なども行っており、新しい技術の活用には非常に前向きです。
CGW:ドローンが防災以外にも活用されているのは興味深いです。
長谷:面白い実験もやりました。ドローンの安定性を試すために、湯前まんが美術館の横から、温泉施設「湯楽里」までケーキを載せて自動航行させたんです。もしケーキが崩れずに届けられたら、将来は災害時の医薬品輸送などにも応用できるだろうと。結果は見事成功。こういう遊び心のある実証実験ができるのも、小さな町ならではのフットワークの軽さだと思います。
CGW:次世代のクリエイター育成にも取り組まれているとか。
長谷:「漫画の町」として、子どもたちの教育には特に力を入れています。地元の小中学生を対象に、崇城大学や熊本大学の先生を講師にお招きして、年に数回、漫画教室を開催しています。
CGW:大学とも連携しているのですね。
長谷:はい。子どもたちがプロから直接指導を受けることで、創作の楽しさを知り、将来の才能が花開くきっかけになればと。ここで描いた作品を「那須良輔風刺漫画大賞」に応募してくれる子もいます。将来的に、進出企業が地元で人材を採用したいと考えたとき、こうした教育の積み重ねが必ず活きてくると信じています。
CGW:大学との連携では、漫画教室以外にも事例がありますか。
長谷:熊本大学には、文化人類学や民俗学が専門で、特に「妖怪」などを研究されている鈴木寛之教授という方がいらっしゃいまして、われわれは深く連携させていただいています。地域の伝承や文化をどうやって面白いコンテンツにしていくか、学術的な視点からアドバイスをいただくこともあります。CGやゲームの世界は、こうした地域の物語や伝承と非常に相性が良いはずです。進出された企業さんが地域の文化資源をヒントに新しい作品を創る、そんな共同プロジェクトが生まれれば最高ですね。
CGW:湯前町をこれからどのような町にしていきたいですか。
長谷:湯前町は「消滅可能性自治体」のひとつに数えられています。しかし、私たちは悲観していません。人口が減少したとしても、デジタル技術を活用すれば、生活の利便性を保ち、農業のような基幹産業も守っていくことができます。
企業誘致は、単に人を増やすだけでなく、新しい知恵や技術、そして文化を町にもたらしてくれます。漫画という文化的な土壌の上で、最先端のデジタル技術と、豊かな自然、そして温かい人の繋がりが融合する。そうすることで、世界中からクリエイターが集まり、ここでしか生まれない新しい価値が創造される。そんな持続可能なクリエイティブタウンを、私たちは目指しています。
CGW:町長は農業に対して強い想いをお持ちですよね。
長谷:ええ、私自身も少しですが農業をやっていますから、食料安全保障の重要性は肌で感じています。地方が元気で、食料をきちんとつくり続けられることが、日本の豊かさを支えている。デジタル技術は、スマート農業実現のためにも強力な武器になります。デジタルコンテンツ企業を誘致することは、町に新しい産業を根付かせると同時に、既存の基幹産業である農業や林業を未来へ繋ぐための知恵や技術を呼び込むことでもある。そう考えています。
CGW:これから湯前町に関心を持つ企業やクリエイターが、実際に町のことを知れる場や機会は用意されていますか?
長谷:まず、10月23日(木)には首都圏でのイベント開催を予定しており、町職員や地元事業者が直接、皆さんのご質問にお答えします。

長谷:また、現地の空気を感じていただける視察ツアーも12月4日(木)と2026年1月29日(木)に1泊2日で実施します。

CGW:湯前町のこれからが楽しみです。本日はありがとうございました。
TEXT__kagaya(ハリんち)
INTERVIEW&EDIT_中川裕介(CGWORLD)
























