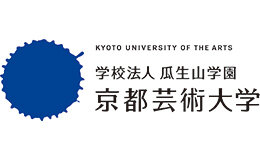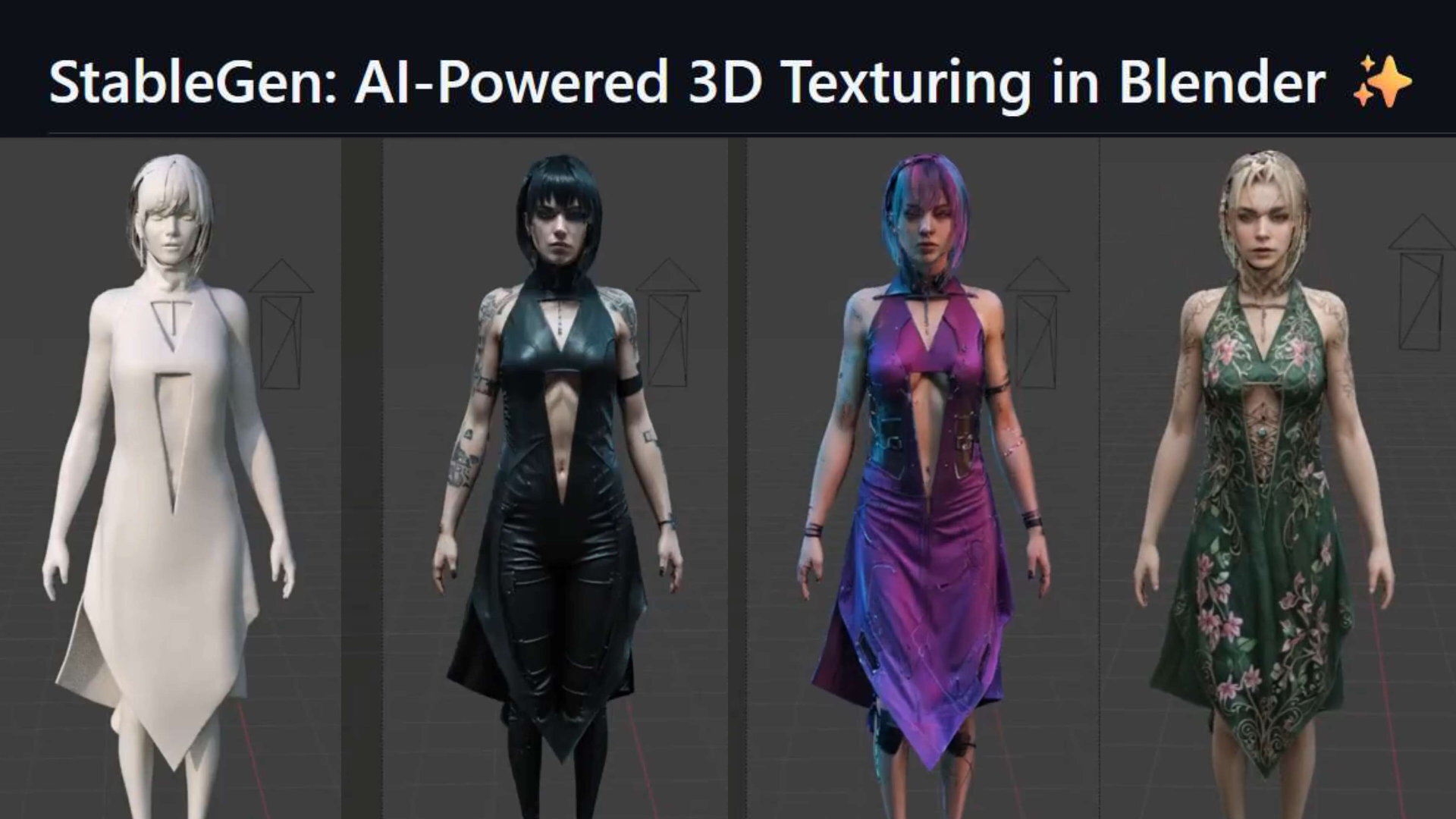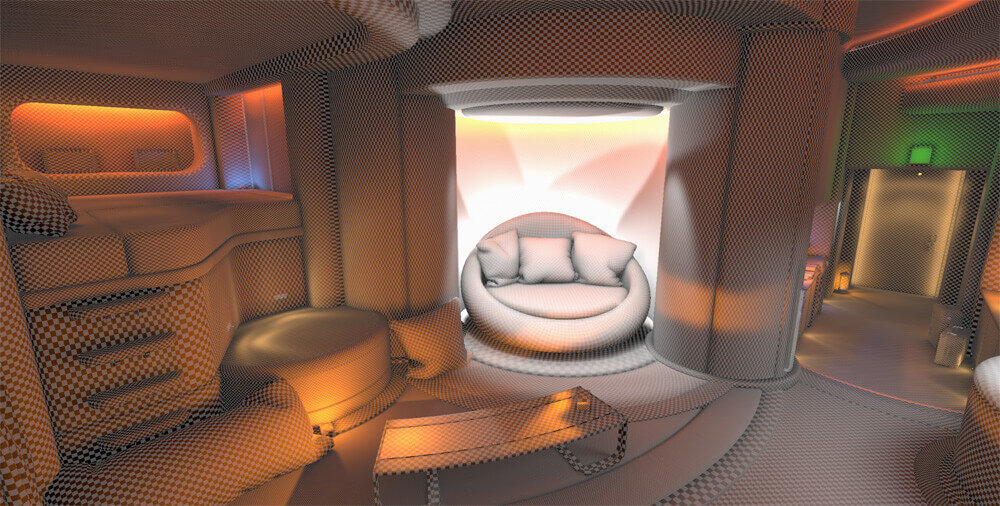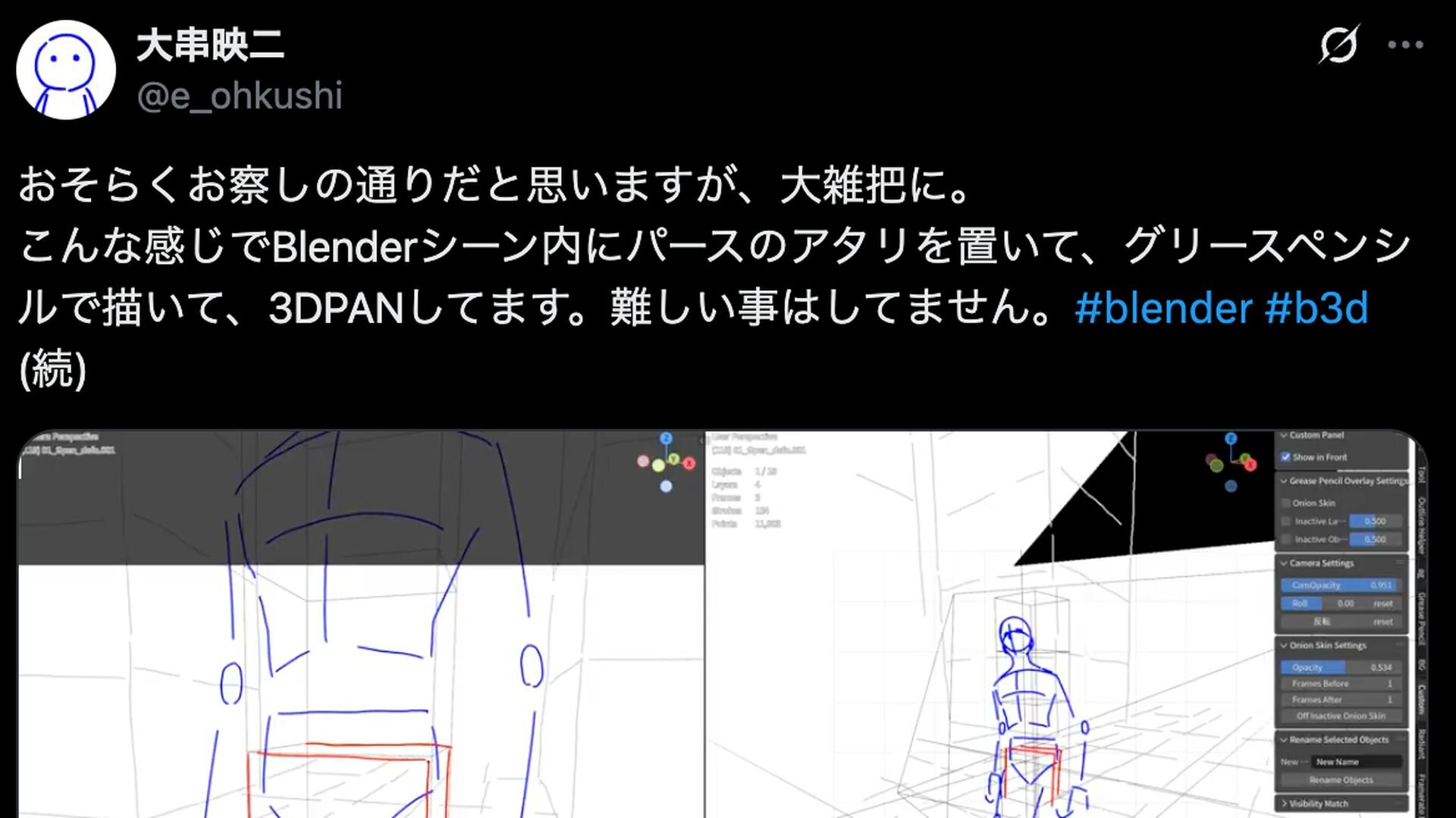「第1回 CGWORLDノベルズコンテスト」では、受賞候補2作品を選出し、CGWORLD.jpにて各作品を全12回にわたって掲載いたします。その後読者投票により各賞を決定し、それぞれ書籍として刊行する予定です。
「CGWORLDノベルズコンテスト」概要
第1回 CGWORLDノベルズコンテスト

■今後の予定
12月8日(金)〜:CGWORLD 305号とCGWORLD.jpで掲載と読者投票スタート
2024年3月頃:書籍時の扉絵イラスト募集
2024年6月頃:読者投票&扉絵イラスト結果発表
本文
初めての変異から、数日。純一は連日のようにノウムに変異し、訓練を続けていたが、未だに自由に空を飛ぶことができないでいた。今日も、すぐに地面に激突してしまい、外傷はコクーンを通して人の姿に戻る際に再生するが、失敗を重ね続け、成功への道が見えない事実は、彼の心に少なからず焦りをもたらしていた。
(何が足りないんだろう……)
「全部だな」「全部だね」とあの兄妹に言われることは明白だったため、純一は独自に方法を編み出そうと考えていた。毎回、翼を動かすことに感情が行きすぎて、その瞬間に意識が途切れてしまう。なら、翼を動かすことに日常から慣れておけばいいのではないだろうか?
その日、マレが食堂の前を通りかかると、本来誰もいないはずのその場所で、異様な光景が繰り広げられていた。
純一が、両腕に樹脂製の板を貼り付け、椅子に上がっては飛び降りるのを繰り返している。
「何してるの?」
食堂での一件以来、純一と会話をすることのなかったマレも、流石に疑問を口にせざるを得なかった。
「練習っ……! こうしておけばっ! ……ノウムになったときにっ! 翼を動かす感覚に……慣れると思ってっ!」
「……そう」
マレが食堂を通り過ぎようとしたところで、大きな音がとどろいた。
椅子から転落した純一は、すねにあざを作り、悶絶している。だが、腕に付けた板で空気抵抗を受ける感覚は、事前に予想していた以上に翼を振るう感覚に近かった。これは大きな収穫だ。
(これを繰り返せば!)
純一は再び椅子の上へと乗る。
「そんな馬鹿なことする必要はないよ」
背後から澄んだ声が聞こえた。振り返ると、そこにはマレがいる。
「えっ、そう……なんですか?」
最後のマレとの記憶は、食堂で爪を突きつけられた一件だ。気まずさと、このような姿を見られたくない心情の両方があったため、純一は慎重に返事をする。
「―今までノウムになるとき、どうやって集中していたの?」
そうマレに問われ、純一は天を仰ぎながら、考えた。
「ひたすら、飛ぶことだけ頭にあるかな」
「そうじゃなくて、もっと……今、一番やりたいこととか、思い出とか、そんなふうなものを思い浮かべた方がいい」
それだけ言うと、マレは食堂の出口へと向かっていった。
「なるほど。ありがとうございます!」
マレが振り返る。
「先生に言われたから」
先生とは二宮のことだろう。そう言って、マレは去っていった。
「あの、この間は変なことを聞いてごめんなさい!」
純一の謝罪に対し、彼女は何も答えを返さなかったが、純一には一瞬、彼女がうなずいたように見えた。
まだ、彼女のことは何も知らない。アドバイスはしてくれたが、彼女は狼の姿になるとき、何を考えているのだろうか……それが少し気になりつつ、純一は次にコクーンに入るとき、彼女が言っていた方法を実践しようと思った。
その日は、ギラギラと輝く日光が中庭全体に差し込む、やや蒸し暑い日だった。純一は、コクーンの前に立ち、深呼吸をしている。
「ここのところ顔を出せずすまなかった。楽しみにしているよ」
訓練の成果を見に来た二宮が、笑顔を純一に向ける。
「そろそろ行けるか?」
コクーンを操作するタンが声をかけた。彼の心中はわからないが、その言葉には「いい加減飛べるようになってくれ」という意味も含まれていると、純一は思った。近頃、二宮は多忙なようで、会話することもなかったが、おそらく同じ心境だろう。着実に、内覧会の日は近付いているのだから。
すでにティトとシーナ、そしてマレは変異を遂げていた。ティトは細い木の先端にあるボールを見事に取ってみせ、シーナは中庭に設置された池の底に所員が設置した機材を、変異前に指定された通りに操作している。マレは、運動能力を試されているのだろうか。中庭に組み上げられたアスレチックの中を、自由自在に駆け回っていた。自分も、早く彼らのように、もう一つの体を使いこなさなければ……。
「行けます」
純一は二宮とタンを見てうなずいた。
「よし、じゃあ入ってくれ」
コクーンに入り、ハッチが閉じ、機械的な音声が流れ始める。ここまではもう慣れたもの。問題は、その先だ。マレは、自分の執着している願望や思い出を頭に浮かべたほうがいいと言った。それを軸に意識、記憶を辿れるということだろう。ならばと純一が考えたとき、彼にとって一番大切なものは、やはり宇宙に行くことだ。純一は、第二波の調査船に乗り、新天地で自分が空を翔る姿を思い浮かべ続けた。それは、今の純一の想像力が許す限りの、理想の自分だ。
―再構成された瞬間、それまでノウムになった際の意識に霧がかかった感覚がなくなったことが、はっきりとわかった。今までは、神経は通っていても、まるで何重もの分厚い上着を着せられているような違和感を純一は抱いていた。しかし、今回は翼の先端まで感覚が行き渡り、自分の肉体として、自由自在に動かすことができる。そして、どう羽ばたけば空を飛べるかも、本能で理解できた。まるで、これまでも、ずっとそうやって空を翔け回っていたかのように。
純一は、今まで通りコクーンの縁に飛び乗ると、思い切り翼を羽ばたかせ、足元を蹴った。
風を掴み、羽ばたくことで加速しながら、どんどん高度を上げていく。風に運ばれてきた草木の匂いが鼻孔をつくのが、たまらなく心地よかった。
下に目をやると、マレとティト、そして水面から顔を出したシーナがこちらを見上げているのがわかった。
(やったぞ!)
純一は気分よく風に乗り、どんどん上昇を続けていく。夢中になるあまり、「それ以上高度を上げるな」という声がシードを通して響いていたのにも気付かなかった。
ある高度まで到達した瞬間、純一の体内に埋め込まれたシードの制御機構が作動し、彼の肉体は硬直した。それまで上昇していた純一の肉体は速度を落とし、静止すると、今度は下に向かって速度を上げ、落下していった。
―深い闇の底に落ちていた意識が、激しい振動と共に引き上げられる。急速に心拍数が上がったのだ。純一が目を開けると、そこにはテトラオキシンを純一の手に打ち込むタンがいた。
「やったな」
タンが笑顔を見せる。その横から、すっと二宮が顔を覗かせた。
「よくやってくれた。あとは、精度を高めていくだけだ」
その顔からは、喜びが滲み出ている。平静を装いながらも、これまでずっと、純一が無事飛び立てるのか、不安を抱いていたのだろう。そんな二人の表情を見た純一は、ようやく自分の居場所を見つけられたような気がした。
四・星空
目の前に中庭の風景が広がっている。視線を上に向けると、雲が背後の陽光によって、ぼんやりと光を放っていた。―そこに狙いを定め、大地を蹴り、思い切り翼を動かす。
ノウムへの変異を繰り返すうちに、純一はかなりはっきりとした意識で鳥となった肉体をコントロールできるようになっていった。
「よし、中庭を一周してみてくれ」
今では、体内にあるシードから響く二宮の声もはっきりと理解し、その指示を実行することができる。純一は中庭に吹く風を翼で切りながら、上空を一周して見せた。
「あの台に着地してみろ」
二度目の指示が飛ぶ。“あの台”とは、中庭の隅に設置された金属製の台だ。純一はそこに近付いていくと、翼の動きを緩め、足を黄色いバツ印が書かれた中心に着けた。
人間の姿に戻って、変異室の壁際に座り込んで休んでいると、管制室からやってきた二宮が純一の前に立ち、見下ろした。
「これなら、内覧会の日には間に合いそうだな」
「本番では何をすればいいんです?」
「基本的には先ほどのように、私の指示に従って飛んでくれればいい。ただの鳥じゃなく、人間が変身しているということを証明するんだ」
「ま、素人にしてはマシになってきたな」
やってきたのは、純一の後に 再構成を済ませたティトだ。
「そう言うな。純一くんも、まだわからないことは多い。いろいろ教えてやってくれ」
二宮がティトをたしなめる。
「でも、実際すごいよ。最初はもっとかかると思ったけど、いきなり飛べるようになってさ。ティトはもっと苦労してたし」
合流してきたシーナが、首から生えた棘を撫でながら言った。
「俺のことはいいだろ」
ティトが軽く舌打ちをする。
「マレが教えてくれたおかげですよ」
純一は、やや目をそらしながら言った。
そのとき、マレがコクーンから出てきた。二宮は、マレに近付いていき、何やら声をかけている。
「今日の調子はどうだ? 左前足の重心バランスが……」
と、会話の一部が純一たちにも聞こえてきた。そんな内容以上に気になったのは、二宮のその顔だ。自分やティト、シーナに向けるのとはまったく別の、優しく、柔らかな表情を向けている。
「へっ、相変わらずだな」
と、苦笑交じりにティトが呟いた。
「そうなんです?」
ティトがうなずく。
「ああ。マレは俺たちの中でも古株だからな。二宮としても、思い入れがあるんだろ」
確かに、ノウムとしての彼女の姿は人目を惹くし、動きも完璧だ。それだけ優秀なら、多少ひいき目に見られても当然のことなのだろう。そう、純一は思った。
「あ、そうだ、純一」
シーナが何かを思い出したようだった。
「なんですか? シーナさん」
「その堅苦しい喋り方はもうやめてって話。私もティトも、ゾワゾワするから」
「そう……ですか」
「ですか? ってなんだよ」
ティトが口を尖らせる。
「わ、わかった。これからもよろしく、ティト、シーナ」
それは、この兄妹なりに、純一を少し認めたことの証だった。ティトは何かと憎まれ口を叩くし、純一もあまり良い印象は抱いていなかった。だが、不用意に馴れ馴れしく近付いた自分にも非はあったと理解していたし、何よりも、同じノウムというもう一つの体を持つ者として、先達の二人が認めてくれたことに、喜びを感じていた。
続きは毎週月・木曜に順次公開予定です!(祝日及び年末年始を除く)
日程は公開リストよりご確認ください。
『美術商ローラと家路を急ぐ青年』はこちらに掲載しています。
読者投票
読者投票は以下からご参加ください。ぜひお気に入りの作品に投票をお願いします!
読者投票はこちらから※締切:2024年1月25日(木)23:59まで
※回答は1人1回までとさせていただきます。